キャリア志向性の多様化と独立者の増加を考慮して、これから企業にできること
- Capire(カピーレ) 伊藤亜里沙
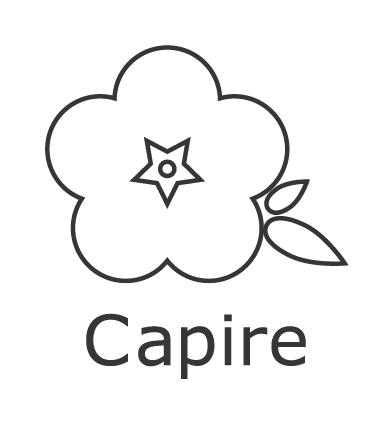
- 4月21日
- 読了時間: 5分
更新日:4月22日
「ポジションを上げていくキャリアに興味を持たない人が増えている」
という話は皆さんもよく耳にすると思います。
一方で、独立していく層は管理職・役員経験者比率が高い状態にあります。
つまり、役職に就きたくない人は増加していて、役職経験者で独立志向の
ある人は会社を辞めてしまっている、ということです。
今回は、企業内の人員構成が変わっていく中で企業にできることの一例を
ご紹介します。
------------------------------------------------
1. 管理職になりたくない人
------------------------------------------------
株式会社パーソル総合研究所(2024年調査) 管理職になりたくない社員がなぜ増えるのか|原因と対策を解説:
「今後どのようなキャリアを考えていますか?」という質問に対して、
「現在の会社で管理職になりたい」と回答した人は、全体で
2021年→24.0%
2024年→17.2%。
毎年右肩下がりで、3年で6.8ポイント下降。
20代の社員で管理職を希望する人の割合については、
2021年→36.4%
2024年→28.2%
と、低下しています。
同社の調査によると、管理職になりたくない理由は、
<20代>
・責任が重い
・業務時間が長い
・報酬が減る可能性がある
→残業代がつかない役職の場合には責任と報酬の逆転が起きることが
ある
・キャリアに関する志向性が上の世代と異なる
<女性>
・仕事と育児・介護のバランスが取れない
・社内にロールモデルとなる女性管理職がいない
というものでした。
------------------------------------------------
2. 独立する人は役職経験者が多い
------------------------------------------------
プロフェッショナルのシェアリング会社の調査データをご紹介します。
株式会社サーキュレーション(2022年調査): https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000015163.html?utm_source=chatgpt.com
会社員時代に管理職を経験している割合は、
女性→65%
男性→88%
です。
業務委託で仕事をするとしても法人として仕事をするとしても、
クライアント企業と対等な立場でプロとして仕事ができる、となると
役職者経験のある人材になりやすいと思います。
------------------------------------------------
3. データからわかること & 企業にできること
------------------------------------------------
これらのデータからわかることとして、以下が挙げられます。
①キャリアの志向性が多様化しているので、階層ごとに一律の育成
プランニングを行うだけでは人材育成は難しい会社が多く、社員が
幸せになりにくい
②役職者は独立していく可能性があることを視野に入れた人材育成が
必要
「では、企業側はどう対応していけば良いのか?」という問いへの
答えはいくつもありますし、企業ごとに事情が異なりますので、
きちんと自社の状態とどうなりたいのかを考えて人事が動いていく
必要があります。
なので、一つだけ私の考えをご紹介させていただくと、
①への対応案:
トップダウン型のマネジメントの時代には「会社が求めるスキルを保有
している人材」に育成していくだけで組織運営がある程度うまくいって
いきましたし、社員も会社の意向に沿って長く働いてくれましたが、
今の時代はそうではないので、「画一型」から「希望者募集&選抜型」の
対応をミックスして様子を見ていくと良いのではないでしょうか。
望んでいない社員を管理職に抜擢することがその人を幸せにしないことも
あるならば、望んでいる人に機会を与えるけれど、人柄を含めた適性を
会社がきちんと見てから選抜型で抜擢する方法に変えれば、多様化する
キャリアニーズにも対応でき、会社も全員への育成投資から希望者への
集中投資に切り替えることができそうです。
(注:希望者が多い場合には育成のための投資金額が上がる会社もあると
思うので、自社の状況を考えて決めてください。)
また、「画一型育成」の弱みは、社員が自身のキャリアを会社に委ねる構造が
生まれやすいこと。
そこで、自身で下したキャリアに関する意思決定にしっかり向き合える環境に
することで、会社側も「管理職になりたい人」を早期に把握し、部署の
サクセッションプランと紐づけしていけば、企業も社員も幸せになれると
思います。
ちなみに、人の気持ちは変化していくものなので、希望の変更はよしとして
運営すると良いのではないでしょうか。
②への対応案:
スタッフでも希望すれば上のレイヤーの研修を受けられるようにして、管理職
育成の時期を早期化させると良いと思います。
極端に言うと、データ上、将来企業内で働いている人たちは
・役員
・管理職は人材層が薄い
・スタッフ
といった人員構成になりやすいということなので、社員の業務遂行力や熱量を
高める意味でも管理職人材・経営人材の育成の早期化はしておいた方が良いと
思います。
職責上、階層ごとにものを見る範囲が異なり、上の職位になればなるほど
俯瞰的な目線が必要になっていきますが、育成の早期化によって上の人たちに
必要な動きが分かったために、自身は今部下としてどう動くことが会社への
貢献になるのか、といった視野の広がりも期待できそうです。
---
時代の変化とともに人事も価値観やこれまでの常識を疑い、戦略や戦術を
少しずつ変えていくことが、組織や人材、事業の発展につながっていきます。
打ち手は一つではないので、貴社に合った対応をディスカッションしてみるのも
おすすめです。
会社のことも、働いてくれている社員のことも、本気で考えたいですよね。
■管理職研修を行っています。
■人事アドバイザリーを行っています。
